
3月1日、柏市立高田小学校で6年生93名を対象に渡辺 章会員が話をした。
自己紹介の後、マラリアの話では、種類やどんな病気か、雌蚊が感染を起こしその防止策として水溜まりを排除する大切さを説明し、 感染数や死亡数なども示した。日本でも海外渡航者が感染し、死亡率も高いという話に、他人ごとではないマラリアのことが子供たちに浸透した。
次のアフリカの話では、子供たちにアフリカの国連加盟国数等について予め調べる課題を提示してあり、アフリカの植民地時代から話を分かり易く進めて、 食べ物等の物価、病院の中の様子や、文化、自然公園にいる動物等の話があった。
大洋州では風疹、はしかなども含めてワクチンプロジェクトを組んで、島々をめぐった活動を紹介。赤道直下の島の様子や年に2回しか舟が行かない島、 人口が7人だけの島など、大きな環境の違いの世界があることについて考えるヒントが与えられた。
最後にJICAの広報ビデオ「何時か世界を変える力になる」が上映され、ブータン、シリア、セネガルなどで実際活動しているJOCVやSVの人達を追ったドキュメンタリで、 活動の内容や現地の様子など、ボランティア活動について子供たちにも非常に分かり易いものだったので興味深そうに見入っていた。
生徒からJICAの活動をして良かったこと?活動に入るきっかけは?などの質問があった。いつもと違う授業で面白かった、自分も将来JICAの活動をしてみたいなど、 子供らしい素直な意見が聞かれ、先生方から目がキラキラしていたと感想を述べられた。

2月15日(金) 平成31年2月15日市原市立有秋公民館で三輪達雄会員が「ブータン王国から見た幸せとは」と題して講演しました。聴講生30名。
ブータンは人口70万、面積は九州とほぼ同じ。中国とインドに挟まれた国境の国、標高100メートルの低地から7,5000メートルの高地まで。公用語は英語。
ブータンの人々は敬虔なチベット仏教の信者で、幸福度では世界一である。収入源の30パーセントは国際援助であり、インドと日本が主たる支援国である。
日本とは平和条約が締結されていなのでJICA事務所がその役割を担っている。人々は親日的である。
協同組合の設立の指導が主目的であったが、設立は簡単なものではなく、先ずは連合会設立のアドバイスや実態調査を中心に行った。 ブータンの課題は中国とインドに挟まれていることで政治情勢を複雑にし、一方、インド、日本などからの援助からの独立を実現する必要を感じた。 ブータンでは若者は変化しており、失業や薬物など問題も多い。自然との共生の維持も問題を含む。
しかし、2年間の滞在で得たことは多く、日本の現代の問題の解決にも参考になるものが多かった。
 昨年の秋募集より、シニア海外ボランティアの名称が、シニア海外協力隊と変更されたのを受け、2月9日(土)、イオンスタイル検見川浜のイベントホールにおいて、
JICA東京後援による、募集・広報イベント「シニア海外協力隊リアル体験談ー世界の果てに住んでみたー」を開催しました。
昨年の秋募集より、シニア海外ボランティアの名称が、シニア海外協力隊と変更されたのを受け、2月9日(土)、イオンスタイル検見川浜のイベントホールにおいて、
JICA東京後援による、募集・広報イベント「シニア海外協力隊リアル体験談ー世界の果てに住んでみたー」を開催しました。
生憎の雪模様にも拘らず、前半が40名、後半が28名と多数の参加者があり、盛会となりました。3時間余りと長丁場でしたが、全部通しで聴かれた方もありました。
プログラムは、JICA海外協力隊の説明、及び会員2名の活動報告でした。最初に15分ほど、JICA千葉デスクの永井氏から、JICA全般、及び、春募集に関する 説明があり、準備した応募書類は全てなくなりました。

次に、岡崎、濱崎両氏から、世界の果てのリアルな体験談が発表されました。岡崎氏は、「日の沈む王国モロッコ」について、1時間半にわたって話しました。 モロッコ王室に関する記事から見えてくる家族関係の違い、音楽活動から見えてくる社会構造の違い等から、人間社会の多様性を考えさせる内容でした。

濱崎氏は、「世界の果てミクロネシア」で違和感を持った6つの体験を説明しました。日本ではありえないという話に聴衆は驚いていました。
元々このイベントは、我々の活動をもっと広く一般の方々に知って頂きたいという、岡崎幹事のアイデアで始めた試験的な企画でした。 その結果、イオン担当者の評価も高く、次のオファーがあり、今後もシリーズで続けてゆくことになりました。このように、今回の自主イベントは 次の活動につながる大きな成果を得ました。
皆様も参加なさいませんか? 多くの方々の講師登録をお待ちしております。

2月7日(木)柏市豊小学校の6年生101名を対象に中村時夫会員がお話しました。
子供たちには予めパラオについて課題が与えられ調べていました。パラオは赤道の北に位置し、人口も2万人程度、豊かで澄んだ海に囲まれ、50kgもあるカジキマグロを 吊り上げる体験ができる。ゆったりと時間が流れる良い環境の中で人々は、オープン な性格で笑いが絶えない。戦前日本により28年間統治されていたこともあり、日本 語や食習慣の一部や神社が残り、さらに現代では、日本からの援助による友好の橋や 道路の整備などもあって、親日感情の強い国である。
配属された教育省では、主に算数教育について小学校1年生から中学2年生までの 学力向上と先生方の能力水準を引き上げるために活動を行った。具体的には九九の間違いが多かったため、全校生徒一斉テストを実施し、一方先生方には、講習会で力をつけてもらった。その指導の結果、短期間で正答率が格段と高くなった。 その他、学校内の行事なども紹介。地域の人たちがドンドン加勢していく運動会の綱引き、走らないバスケットボールの競技など面白く紹介されたので、子供たちが笑ったり、手をたたいたりしていた。講師は小学生向けの話し方になれていて、所々、質問を入れ生徒に考えさせ、手をあげさせていたので、生徒たちは、最後まで興味深く聞き入っていた。最後にパラオの子供たちは、貧乏でも校内ではいじめなどはなく、明るく、仲良く一勉強していることと、将来意思があれば、誰でもJICAの活動で世界中へ行けることを紹介した。子供たちから食べ物は?スポーツは?など関心のあることについての質問があり、45分はあっという間に終わった。
| 1月25日(金)午後1時より柏市のアミュゼ柏で、来賓としてJICA東京次長長谷川氏、浦安市国際センター長渡辺氏、 柏市協働推進課村山氏、野田市企画調整課峯崎氏を迎え、帰国した海外派遣シニアボランティア4名による第26回活動報告会が行われました。 一般参加者11名、会員34名、来賓4名、計49名の参加がありました。 |
 渡邉会長 |
 長谷川次長 |
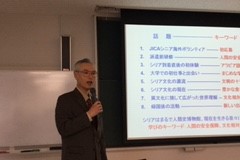
高瀬義彦講師による「シリアでイスラム文化とキリスト教文化に接して広がった世界理解」と題して、うらやす市民大学のオープン講座第六回目が12月19日に開催されました。
以下の講義内容には随所に自身の『気づき』が含まれていました。
- JICAシニアボランティア応募
- 派遣前研修 キーワードとして人間の安全保障、文化相対主義
- シリア着任後の現地研修、大学での仕事、 学生の創意工夫に感激したこと。
- シリア文化の源流 BC1世紀から3世紀にかけての源流を紹介
- 現在のシリア文化
- 異文化に接して広がった世界理解 文化相対主義の『気づき』
ここが講義の山場です。自身の考え方を明瞭に示し、受講生に異文化に対する気づきを与えていました。 - 帰国後の諸活動紹介
全体的に任地の紹介だけでなく、上記の項目の中でキーワードの提示、自身の気づきを受講生に示しており、 うらやす市民大学の理念に合致した講義内容でした。
なお今回で今年度うらやす市民大学オープン講座JICAシリーズは終了となります。この講座は科目名『開発途上国から学ぶ』として 来年度の本校の正式科目として認可されています。

12月18日(火)午前11時、JICA海外協力隊帰国者9名、派遣者12名計21名が千葉県庁を訪問しました。
JICA東京次長が来賓を代表して挨拶し、海外援助の難しさを語り、「思った通りにはならないが、やった通りになる。」という自身の体験を語って労った。
その後、帰国者及び派遣者が自己紹介をして抱負を語りました。
最後に県庁を代表して今泉総合企画部長が帰国者の労を労い、出発の隊員に開発途上国で活躍したいという貴い志に敬意を表し、お願いとして、千葉県代表として千葉の宣伝を御願いしたいと述べ、又赴任国では健康に留意されご継役を願っていると述べました。
最後に全員でマスコット・チーバ君と集合写真を撮りました。

12月11日(火) 講師 浜崎 丘 会員
山武郡横芝光町上堺小学校において、全校生100名、先生・一般20名を対象に出前講座を行いました。
2020年のオリ・パラでベリーズの選手団を受け入れるホストタウンになったので、生徒に同国の予備知識を与えるために出前講座が要請された。
講師の仕事はゴミ処理場の技術指導であった。まず、同国の国旗の図柄から始まり、人口、面積、国花、国鳥、文化遺産、動植物、そして人々 の生活、食べ物、多数の人との密な交流等について多数の写真をもとにベリーズの実情を話された。
話し相手は1年生~6年生という幅広い対象でありました。3,4年生を中心として、小学生の目線で、理解できるように工夫をして巧みな話術で講 演された。予め下調べをしたこと、および生徒との活発な対話方式で講演 したので生徒の理解度も増し、あっという間に1時間が過ぎてしまいました。
生徒たちはベリーズとはどのような国かというイメージを掴むことができたように見受けられた。

12月11日(火) 講師 浜崎 丘 会員
山武郡横芝光町大総小学校において、全校生39名、先生・一般17名を対象に出前講座を行いました。
出前講座の要請理由は上堺小学校と同じです。講師はゴミ処理場の技術指導を行いました。
先ず同国の国旗のデザインを丁寧に説明してベリーズの大まかなイメージを把握させることから始まりました。次いで地理、 国勢、文化、自然、動植物などについて人々の生活、食べ物、多数の人との密な交流等についてベリーズの実情を話された。
話し相手は1年生~6年生という至難の講演でしたが、小学生の目線で、生徒と直接対話、質疑応答しながらアクテイブ・ブラーニングという手法 を用いて話をされた。生徒が予め下調べをしたこと、生徒との活発なやり取り、学校側の熱心な態度により、生徒はベリーズがどのような国である のかということが把握できたと思われた。

中村時夫講師による「パラオの素敵な人々」と題して、うらやす市民大学のオープン講座第五回が11月28日に開催されました。
JICAへの応募動機、訓練所でのエピソード、派遣国での活動状況、帰国後の社会活動などを時系列的に分かり易く説明されました。
仕事の話の合間に遊びのスライドを入れるなど、講演自体が工夫されていました。講演者は巧みにユーモアを交え、受講生は退屈と感じることは全くなかったと思われます。 また、自身の体験談が一貫して人助けであり、今もそれを続けられている、ということが受講生に感動を与えたようです。
受講後のアンケート結果からも、この講義を通じて受講生は今後の自分の生き方まで考えさせられたという意見が多数ありました。
ボランティアスピリットの神髄とも言える中村講師の素晴らしい諸活動についての講演であったと思われます。
今年度のうらやす市民大学JICAシリーズオープン講座は残すところあと1回です。毎回受講されている方からは、あと1回で終わるのは残念である、 とも言われています。

11月22日(木)八千代市八千代公民館で、自主講座「JICAボランティアが語るリアルな世界事情」の第3回目が行われた。 講師は当会の鈴木伸一会員で、18名の視聴者に「ケニアで何を体験し、どう感じ、何を得たか」について話をした。
ナイロビの健康保健省で、国の国勢調査のような集計作業のコンピューター化プロジェクト立ち上げに協力した過程から見えてきた、 ケニアの実情が話された。
地理的位置や簡単な歴史、気候などから始まり、見聞した現地の人々の生活が写真、ビデオを多用して紹介された。 さすがにアフリカまで旅行した人は少なく、特に日常の食事・料理の作り方まで紹介されると、みんな興味深げに聞いていた。

11月17日 袖ヶ浦市平岡公民館において、中井邦夫会員から「 中東の風・ヨルダンの暮らし」と題して出前講座を行いました。
最初に、JICAボランティアの活動の説明があり、ヨルダン基礎情報、歴史、現在に至るまでの状況を話してもらった。
特に現在話題も多い中東情勢、東部の石油産油国の様子やヨルダン川西側の違いなど聴取者の年配者の方々にもわかりやすく興味の湧くような話題も多かった。
次にヨルダンでのホームスティの状況やアラビア語の説明、家族の生活や子供の教育の内容までおよび実生活がよくわかった。
以下概要の説明となった。
1. ヨルダン大学での活動内容
青年海外協力隊とのコラボレーション
2. ヨルダンでの人権問題
3. 国連パレスチナ難民救済事業機関の状況
4. 政府開発援助(ODA)による支援状況
5. ヨルダンに逃れるパレスチナ、シリア難民
この後、ヨルダンの観光地の説明もあり、死海のビーチ、JICAが建設した展示館で死海の水位が年々下がっており、2050年には水がなくなる恐れがあること。これは途中のヨルダン川の水が灌漑用水に使われていることに起因しているということです。
また、国内の有名な遺跡、数日前洪水により日本人47名がかろうじて避難したこと等です。
「バヌアツとは?」と題して、白鳥 貞夫講師による柏市立風早南部小学校の出前講座が11月6日に開催されました。
小学校の6年生40名を対象に、自己紹介の後バヌアツの位置から話を始められました。その後、バヌアツの人口や言葉などについて、 3択のクイズ形式で進められたため、子供たちの参加意識が高い授業になりました。
特に、人口については柏市の半分しかないことを知り、皆驚いていました。また、言葉の数が100以上もあり、隣の村に行くと言葉が通じないことなどは、 子供たちには信じられないようでした。任地での活動についても説明され、貨幣経済が未発達のところでビジネスについて教えることが大変だったと話すと、 「なぜお金がいらないのか?」といった質問も出ました。その後、バヌアツの風景や生活について、多くの写真を用いて紹介されました。
また、世界の幸福度ランキングではバヌアツが一番にランクされていることを紹介し、その算出方法ついても説明されました。
最後に質問の時間を設けると、「どんな食べ物をどのように料理して食べているのか?」とか、「虫も食べるのか?」などという質問だけでなく、 「地球温暖化がバヌアツに与える影響は?」といった難しい質問も出、最近の小学生のレベルの高さを知ることができた授業でした。

山崎豊講師による「アジアの国々から学ぶ」と題して、うらやす市民大学のオープン講座第四回が11月2日に開催されました。
教員現職時に休職して、協力隊でネパールで活動したことを述べられ、その後、シニアボランティアとしてスリランカで活動されていたとの紹介がありました。 スリランカの説明の中でジャヤワルダナ大統領の日本への貢献の話をされ、参加者は感銘を受けていたようです。現地での活動内容、自身が学んだことなどについて わかり易く説明されていました。
これからの自身の取り組みで「数学を英語で教えること」の重要性ならびに、自身の経験をもとに日本人がどのように考えていくべきか、という課題の提供などもありました。 広範囲な内容になっていましたが全体的にスライドが良く出来ていました。
また前回同様、リピーターが数名いらっしゃったようです。今年度は今回の講師である山崎氏の他に、さらに2名の講師によるオープン講座が2回計画されています。

11月1日(木)八千代市八千代台公民館の自主講座「JICAボランティアが語るリアルな世界事情(全3回)」で、29名の視聴者を対象に、篠原会員が第2回目として「首都プノンペンの教育と学校建設」のテーマで出前講座を行いました。
最初に視聴者の方の中からカンボジアに行ったことある何人から、カンボジアの印象や今感じていることなどを聞かれ、その後カンボジアの実情などを話されました。
そして、カンボジアでの活動の状況、教育の現状、その中で活動上の苦労された話など数多くの話題に大いに盛り上がりました。特に学校さえない状況でどのように 教育がなされているのか?今後どのように教育目標を作っていくのかなど、難問が多いことなど実体験を踏まえた講話の内容は心をひきつけるものでした。
その中でJICAが果たしている役割など国際協力の重要性も強調されました。
最後に、カンボジアでの日本企業の進出状況、日本語コンテストの実施、サッカーの本田選手がカンボジアの代表監督になったことなど話は盛り上がりました。

2018年10月25日市原市五井公民館「創年ふれあい塾」の一環として、弓貞子氏による「エクアドルの青い空の下で~JICAシニアボランティア活動体験~」と 題した出前講座が開催され、80名もの聴衆が熱心に耳を傾けました。
講師は、看護師・助産師として病院勤務を経て、長年、短大で看護教育に従事、そして義母の介護の後、キャリアを生かしたセカンドライフのスタートとしてSVに 参加したこと、また、訓練所で初めてスペイン語を学んだ苦労話から講演が始まりました。次に、ガラパゴスの動物、生い茂るバナナ林など、多数の微笑ましい写真の スライドを用い、エクアドルという国名の由来、今年は日本との国交樹立100周年、野口英世の黄熱病治療貢献などのエピソードを交えた巧みな話術に、 聴衆は引き込まれていきました。
また、ボランティア活動について、国立ボリバール大学での授業、病院や保健所での実習指導では、物不足や貧弱な設備、衛生状態の問題等、厳しい環境の中、 頑張って実習現場の戦力となる学生達の様子のほか、標高4200mのコミュニティで、同僚・学生と共に行った健康・生活改善プロジェクトや、 「世界の笑顔のために」を利用した備品整備、他のJICAボランティアと実施した医療過疎地への巡回健康啓発活動などが紹介されました。
最後に、現地の生活について話され、言葉の壁、インフラの不備など不自由なことはあっても、人々はおおらかで優しく、親交を深めることができたことや、 貧しさについて考える良い機会となったことなど、二年間の成果、収穫を述べて、大きな拍手の中、講座を終了しました。 素晴らしい秋晴れの下、帰宅する塾生の顔は満足な笑みにあふれていました。

10月18日(木) 八千代市八千代台公⺠館の自主講座「JICAボランティアが語るリアルな世界事情(全3回」」で、24名の塾⽣を対象に、村田会員が第1回目として「南米の日系社会で暮らして」のテーマで出前講座を行いました。
会場には、予めブラジル移民に関する本、パラグアイの民芸品、マテ茶の茶器、移民の生活が分かる写真等を多数展示し、 話す内容が具体的に解り易いよう準備が十分になされていました。
最初に、専業主婦がどうしてJICAボランテイアに応募することになったのか、という経緯を語り、特に女性の聴衆の心を引き付けていました。
途中の休憩時間には、マテ茶をふるまい、事前に配布した南米クイズ問題の答え合わせで和やかな雰囲気を作りだしていました。
話の内容は、南米移住の歴史、ブラジルとパラグアイの日系人の現在の⽣活の様子、任地での活動・生活、日系人が尊敬されている存在であること、東北大震災の時に、パラグアイの日系人社会の人々が東北を支援してくれたこと、を話しました。 最後に、海外ボランティアから学んだことを述べ締めくくりました。
聴衆からは、「素晴らしい内容だった。」「友達も連れて来れば良かった。」の言葉がありました。

濱崎 丘 講師による「南北に長い国チリ」と題して、柏市立旭東小学校の出前講座が10月12日に開催されました。
小学校の6年生43名を対象に、チリの概要から話を始められました。事前に、担任の先生を通してチリについて調べるよう要請を出していたため、講師が質問を投げかけると、生徒たちは積極的に手を上げ答えていました。答えが間違っていることを恐れずに発言することを求め、答えに対しては拍手で褒め称えたため、講座は双方向的で活発なムードで進んでいきました。「国の花」や「国の鳥」などについては、日本の例なども示しながら説明しました。 チリにある「世界遺産」についても、単にチリの「世界遺産」を紹介するのでなく、イースター島やマチュピチュの写真などを紹介しながら、「自然遺産」と「文化資産」、「複合遺産」の違いなども解説されました。また、任地での活動を見せながら、スペイン語の挨拶を生徒に声を出して練習させ、 現地の人々との付き合い方を分かりやすく教授しました。
最後に「コミュニケーションをうまくとるためにはどんな勉強が必要か?」という、難しい質問にも丁寧に答えられました。 スライドの操作を生徒さんに担当してもらうなど、参加型の講座を意識した素晴らしい内容でした。

三輪達雄講師による「ブータン王国から見た幸せとは」と題して、うらやす市民大学のオープン講座第三回目が10月5日に開催されました。
中国、インドの2大国に隣接し長年、安定を保ってきた小国の状況について、任地に駐在した経験に基づいた講演が行われました。
活動を通して得られた現地人のメンタリティなどについても触れられ、さらに地政学的に難しい位置にある小国が、貫いてきた独特の幸福感について講演者は 自身の意見も取り入れてわかり易く説明されました。
参加者39名は皆、熱心に講演を聞き、質問も多数出されました。 今回は浦安市役所から複数の職員の方も聴講されました。また前回同様、リピーターが数名いらっしゃったようです。 今年度は今回の講師である三輪氏の他に、さらに3名の講師によるオープン講座が3回計画されています。
以上