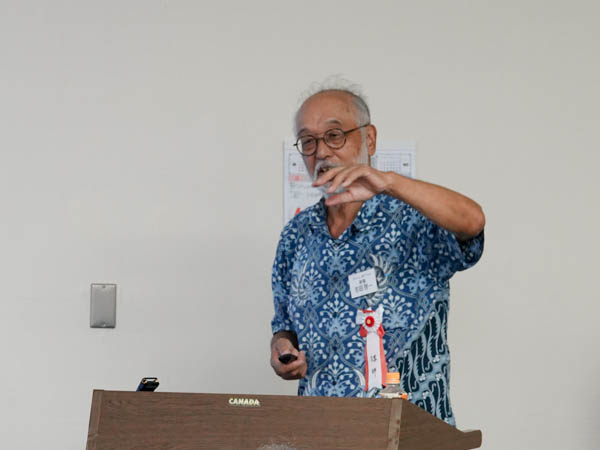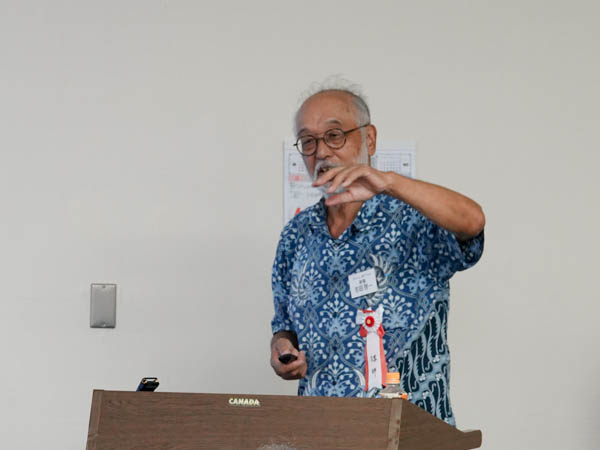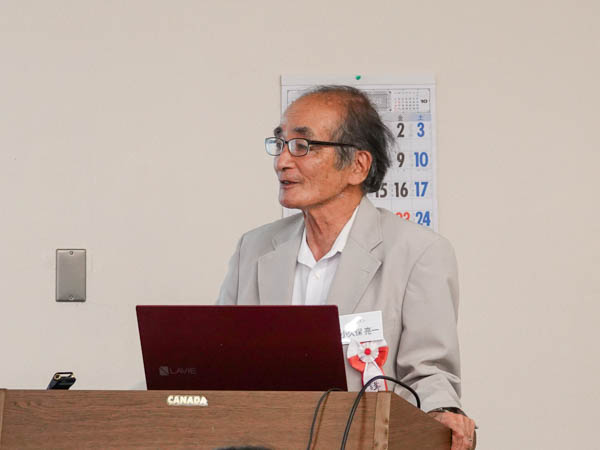第33回活動報告会 - 2022年9月10日
The 33th activity briefing session on Sep. 10, 2022 13:30-17:00
- 場所:千葉市国際交流協会 2階会議室
- 主催:千葉県JICAシニアボランティアの会 共催:JICA東京国際センター
- 後援:千葉県、千葉市教育委員会、千葉市国際交流協会
- 来賓者(敬称略):JICA東京センター所長 田中 泉
JICA千葉デスク 木村 明日美、JOCV千葉OB会会長 西村 邦夫

活動報告: 吉田 啓一(職種:建築)「南アフリカの職業訓練の課題」

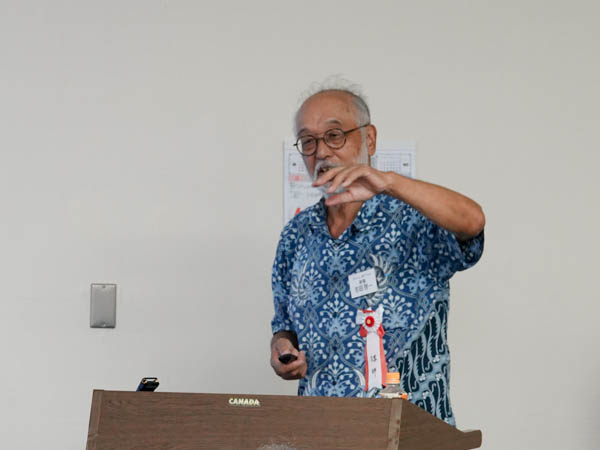
報告の概要
任地は首都ヨハネスブルグから450km離れた人口一万人余りの小さな町で、鉱山開発とともに発展した町である。
職場は、鉱山の黒人労働者の居住区に設置された職業訓練校で、教員、職員の多くが黒人で生徒は全員黒人である。
アパルトヘイト政策が終わり、職業訓練でも黒人への優遇政策が進んでいる。
生徒には授業料のほか宿泊、移動、食事にかかる費用が支給され、黒人への生活保護とも取れる。
教員の多くは資格を取得しているが指導レベルが低いことから、社会が必要とする学力、技術を習得できず、就職率は3%と極端に低い。
一方、出前講座で訪問したケープタウンの訓練校は大きく異なっていた。
校長はじめ教員の多くが白人で、生徒も半数は白人とアジア系であり、授業中に庭でトランプ遊びする生徒は見られず、教員は熱心に指導していた。同校では卒業生の約半数は就職する。
黒人優遇措置が有効になり職業訓練が改善されるには強い政府の指導が必要と感じた。
南アフリカは自然豊かで国立公園に行ったら、像、シマウマ、カバ、運がよければライオンを見られる。
ほんとにいい所です。ケープタウンに行けば食事がとても旨い。
ドライブも楽しくって、いい思いをしたが、今日は堅い話ばかりしました。
聴講者からの質問
Q: マンデラさんの後、資源はあるが逆に後退している気がするがどうか?
A: 黒人優遇政策は良く分かるが、貧しい人達を上げるために、今28年経つが時間がかかり効果があまりでない。
貧しい人たちが成長すれば資源はあるので伸びる国だと思うが、今が良ければよいという雰囲気は感じた。
Q: 暴動が起きたが、移民から仕事を奪われる、経済の悪化など理由は何か?
A: 近隣諸国から数泊万人違法で働きに来ていると聞いた。
結局南アフリカの人たちは仕事を奪われている。小さい暴動は身近にも起こった。
Q: 全体像から職業訓練校はどのようなのか、学科構成などは?
A: 2つのキャンパス(事務系、技術系)があった。事務系では観光やアドミニストレータなど、技術系はIT、建築、電気、地域により細分されている。
活動報告: 小久保 亮一、小久保 弘子(元随伴家族)(職種:環境化学、化学工学)

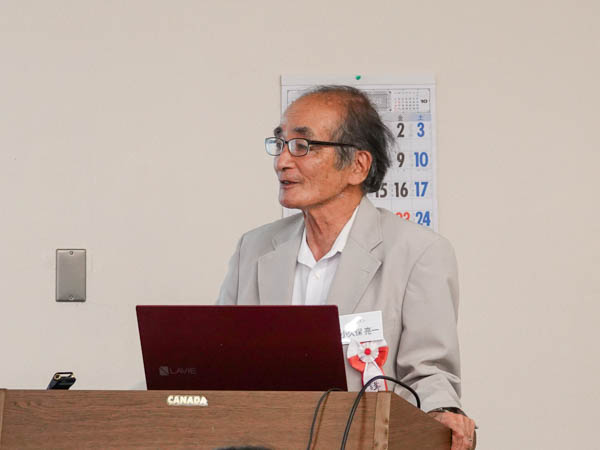
報告概要
派遣国はヨルダン、派遣年は2001年春から2003年春、2003年秋から2005年秋、職種は1回目が化学工学派遣先は職業訓練公社化学技術訓練学院、2回目の職種は環境化学で派遣先はヨルダン国立ヤルムーク大学です。
派遣期間中の任国の事情はパレスチナとイスラエル紛争が最も過激な時期で隣国イスラエルへの渡航は禁じられていた。
またヨルダン国内のパレスチナ難民キャンプを支援するためのバザーが大使館主催で頻繁に行われていた。
随伴家族は自分の得意分野を生かしてこの救援活動に参加していた。
中東とは外務省の定義で15カ国にもなり、また文化についてもメソポタミアとエジプトと、二大文明発祥の地に挟まれている。
文化の内容も大変広いが、私がお話しできるのは、ヨルダンとその周辺のごく限られた歴史と文化に限られます。
随伴家族の活動
随伴家族として4年間パレスチナ・アンマンで暮らして、たえず戦争が起こっているような国ですが、その中で、とても美しいものがあったということをお伝えします。
パレスチナ刺繍と言って、この本はドイツ人の女性が英語でパレスチナ刺繡とは何かを書いた本です。
アンマンの本屋で手に入れて、家で辞書を引き引き翻訳してみました。
昔、ユダヤ人が入植する前は、パレスチナ人がずっと住んでいました。
いろんな地方に分かれていて、例えば、ガザ地区というのは良くニュースで聞く場所ですが、それ以外にもいろいろと地方があります。
私がお話ししたいのは、地方によって、刺繍のパターンが決まっているという所です。


活動報告: 登内 明(職種:経営管理)「異文化理解について」


自己紹介
海外滞在歴は18年 鉄鋼メーカー在職中:米国7年、タイランド5年、スペイン2年、
退職後JICA から派遣:ジャマイカ3年、ベトナム1年
講演者の海外5か国駐在から体験してきた外国異文化をもとに、異文化に対する考え方を総括します。
文化の定義
文化とは人間が社会の成員として獲得する振る舞いの複合された総体のこと。
社会組織ごとに固有の文化があるとされ、組織の成員になるということは、その文化を身につける(身体化)ということである。
人は同時に複数の組織に所属することが可能である。異なる組織に共通する文化が存在することもある。
振る舞いに影響する要因
自然環境(気候、食料、海洋、生物形態、疫病、領土、国境など)
人的環境(教育、習慣、政治、経済、人口動態、年齢、身体的特徴、芸術、宗教、技術など)
参加者への質問
Q: 皆さんにとっての異文化の人とはどのような人のことでしょうか?
Q: [日本の文化]から何を思い浮かべますか?3つまで思い描いてください。
見える文化とと見えない文化
自分にとって常識とは?
まとめ
- 報告者各位は、パワーポイントで作成した資料を使って、動画なども取り入れ分かりやすく活動を報告したことにより、
現地の様子がよく理解できた。
- 吉田氏はアパルトヘイトなどの背景にもふれられ、現在の南アフリカの職業訓練が抱える問題点を中心に解説された。
質問への回答も具体的で、現状と問題解決の困難さも良く理解できた。
- 小久保氏はヨルダンとその周辺の歴史と文化を詳しく述べられたが、時間が足らず残念であった。
随伴家族のパレスチナ刺繍の写真の他、実物も展示されたので分かり易い説明だった。
-
登内氏の、参加者に文化に関するいろいろな項目について質問して意見を出してもらう進め方が新鮮であり、
一方通行にならず良い雰囲気をつくっていた。
Copyright © Chiba JICA Senior Volunteers Association